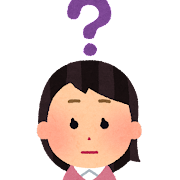ごきげんよう。きいです。
先日、私のゲシュタルトが崩壊しました。
あの、ヘルパーさんの「吸引と経管栄養の実地指導」の指導看護師をしたときに。
ゲシュタルト崩壊とは、知覚における現象のひとつ。全体性を持ったまとまりのある構造から全体性が失われてしまい、個々の構成部分にバラバラに切り離して認識し直されてしまう現象をいう。近年、同じ語を長時間凝視し続けていたり、何度も繰り返したりしていると,次第にその意味が減じられる現象として扱われることがあるが、誤りである。幾何学図形、文字、顔など、視覚的なものがよく知られているが、聴覚や皮膚感覚、味覚、嗅覚においても生じうる。1947年、C・ファウストによって失認の一症候として報告されたが、持続的注視に伴って健常者にも生じることが知られるようになった。認知心理学の視点から「文字のゲシュタルト崩壊」が研究されている。これは、例えば同じ漢字を長時間注視しているとその漢字の各部分がバラバラに見え、その漢字が何という文字であったかわからなくなる現象である。
…って、Wikipediaには載っていましたが。
さっぱりわかりません(笑)。
私に起きたのは「文字のゲシュタルト崩壊」だと思います。
ヘルパーさんが安全に吸引・経管栄養の手技を手順通りに行うことができれば、その項目に「ア」をチェック表に記入します。
1,訪問時、第1回目の流水と石鹼による手洗いを済ませておく。
2,医師・訪問看護の指示を確認する。
3,利用者本人あるいは家族に体調を聞く。
…こんな感じのチェック項目を、クリアできればその都度「ア」。
人工呼吸器を装着している利用者の口腔内吸引のチェックは約30項目。
人工呼吸器を装着している利用者の鼻腔内吸引のチェックは約32項目。
人工呼吸器を装着している利用者の気管カニューレ内吸引のチェックは約33項目。
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(滴下)・経鼻経管栄養のチェックは約16項目。
※研修機関の採用する、評価表の書式によって多少の違いアリです。
全部の項目に「ア」がついて1回目合格。
それを2回繰り返し、2回目も全部「ア」となって認定書が発行されれば、そのヘルパーさんは利用者様個人に吸引と経管栄養を行うことができます。
指導看護師は1回の実地研修でヘルパーを合格とするために、評価表に「ア」を約200回記入します。
「ア」を約200回書き続けたら。
「ア」って、こんな字だったっけ???
「ア」っていう文字は、本当に「ア」で合っているのか?
…ってなってしまいました。
そして、最後には「私、何やってるんだろう?」ってね(笑)。
これ、まだ指導を受けるヘルパーさんが一人だから、まだ良いんです。
これがお二人となると…。
…お察し下さい。