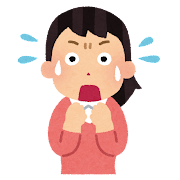ごきげんよう。きいです。
前回の記事<まりぃさんの様子>で。
まりぃさんが、車椅子でみんなと一緒の場所にいられて、トイレや浴室へ移動させてもらえること。
本当にありがたいことです…と、書いて。
最近続いた、施設の入浴支援中の死亡事故について考えました。
いろいろ、施設の事情・設備の事情・業務の事情等があるとは思いますが…。
そもそも。
自分が、目の前の誰かに。水やお湯を使う時。
温度は大丈夫かな。勢いは大丈夫かな。本当に自分が使おうと思っている液体に間違いはないだろうな?って、確認をすることは必要。
介護の場面じゃなくって、育児の時に。
赤ちゃんをベビーバスでお風呂に入れる〝沐浴〟の時。
温度計でお湯の温度を測りましょう…ともいうけれど。
「まずは自分の肘で温度を確認!」が習慣になるほど、身についています。
(ベビーを看ていたころに身につけた習性?)
今も陰部洗浄や創部洗浄のお湯の温度。
シャワー浴、入浴介助の時の浴槽内のお湯の温度。
必ず自分の手で確認をします。
そして「今、これくらいの温度だから。利用者様の身体に使う時には、温度はどれくらいに変わっているだろうか?」を推察して準備します…よね?
すごく大切なことで。
そして「基本中の基本」であるのに。
それがなされなかったのは、大問題だと思う。
どこに原因があったのか。
きちんと考えるべきだと思います。
そして。
高温のお湯で、命に係わることになったから事件になったけれど。
これが「冷水で」「命に係わらなくて」「利用者様が訴えられない人」だったら。
とても怖いことです。
浴室で行われるケア。
いろいろな危険があるということを、みんなが自覚するべきだと思います。