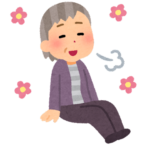ごきげんよう。きいです。
以前<ひきこもり支援推進事業について>では、国や自治体が行っている支援についてお伝えしました。
ひきこもりと言っても、どこまでのひきこもり具合かは様々。用事があれば外出できる方もいれば、自室からほとんど出ない方もいる。
就学や就労ができず親に依存する生活が続き、親が亡くなった後には益々生活が困難になる。
そんな何かしらの支援が必要な方が、今の日本には何十万人といて。
何も変わらないまま時間が経てば…。
親もひきこもりの子供も、そのままどんどん年を重ねていく。
支援を受けることでひきこもりを脱し、社会生活を健全に営めるようになれば、それは素晴らしいことですね。
だけど…そのひきこもる本人にとっては…喜ばしいこととは言えないのかなぁ?と思うのです。
もともとの何か(精神疾患や発達障害など)があることも。
家で親に依存して暮らすことは「外に出るより、守られていて居心地が良い」のも分かる気がする。
だから何年・何十年と引きこもっていられるのだろうし。
実際に「出なくても生活できている」という現実もある。
親も子供を無理に出そうとは思っていないのかも知れない。
ひきこもった期間が長ければ長いほど、社会の荒波にのまれに行く勇気が出てこないのも分かる気がする。

本当に勝手なことを言ってごめんなさい。
家から出ずにいるには、それなりの理由と「出ない」という強い覚悟があってのことかも知れないのに。
幼いころからの家庭環境や、教育の現場での体験、社会での体験の影響もあって、本当に複雑で難しい問題なのに。
家から出て、健全に社会生活をおくれるよう支援する国や自治体と、家を出る気持ちと勇気と機会に恵まれれば「それができる」方々が、この事業を通して巡り合えればいいなと思います。
活動報告
ひきこもり支援推進事業の活動報告がどこかで見れるかな…と思ったのですが、まだ報告は少ないようです。
どうやら支援を検討中の自治体や、まだ行っていない自治体もあり、支援状況にも差があるようです。
そして支援を始めている自治体でも、まだひきこもりの実態把握ができていなかったり、把握したデータをとりまとめられていないことも。
それでもしっかりと結果報告を出している自治体もあります!
皆さんのお住まいの自治体はどうですか?
「実態把握も困難」なことに取り組むことはとても大変です。
だけど、それが求められているのです…。
「頑張れニッポン!」と声を上げるのは、スポーツの大きな大会の時だけではなく、日常の出来事でも言っても良いのかも知れない。